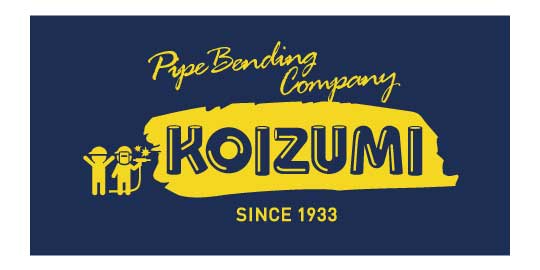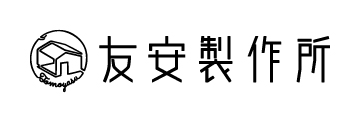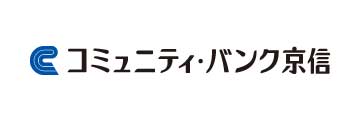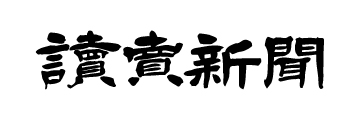小さな機械で広がる大きな世界
マニアックだけど、暮らしに近い研磨の仕事
Episode
語り手
代表取締役 秋山 大輔
マーケティンググループ 佐藤 紘也

小さな現場にフィットする機械、材料を届ける
1986年に創業した有限会社秋山産業は、幅広い業界を顧客とした研磨機械、研磨材料メーカーである。研磨とは、金属や樹脂などの表面を削って滑らかに整えたり、光沢を出したりする加工技術を指す。秋山産業では、砂粒を高速で吹きつけて表面を加工するサンドブラスト機や、部品を大量に入れ振動や回転によって一括で磨くバレル研磨機などの小型研磨機械、および研磨材料の製造・販売を行っている。
同社の大きな特徴は、小規模な現場でも導入しやすい製品・サービスを提供していることである。
研磨機械といえば、一般には工業用の大型設備が想起されるが、同社の製品はそれとは異なる。100Vの家庭用電源で使用できること、限られた作業スペースにも収まるサイズ、そして1人でも設置・移動が可能な軽量さが特徴で、小規模作業場や研究開発部署などのニーズに応えた仕様となっている。
研磨材料については、20kg単位などで流通しているのが一般的であるが、1kg入り包装や5kg入り包装などの少量パックで販売するなど、「必要な分だけ手軽に購入したい」という声にも柔軟に対応している。
このように、同社の製品とサービスは、徹底してユーザー目線で設計されている。
研磨という作業は一般には馴染みが薄いが、その用途は意外に幅広い。工業界のみならず、たとえば歯科業界では詰め物や入れ歯の仕上げ加工に用いられ、工芸分野ではガラスアートやアクセサリー制作、さらには酒瓶への名入れや墓石彫刻などにも使われている。近年では、個人の趣味や小規模ビジネスに携わるユーザーの中で、サンドブラストやバレル研磨といった特殊な表面加工用途に対するニーズも高まりつつある。
秋山産業が工業界に捉われず幅広い市場に対応する体制を整えてきた背景には、現会長(初代社長)の存在が大きい。もともと研磨機械の商社に勤めていた会長は、営業としての経験を活かし1986年に独立。当初は製造業ではなく、卸売を主軸とした事業展開を図っていたが、自身が日曜大工を趣味としていたことから、次第に機械そのものの製作にも着手するようになった。
こうした「ものづくりの原点」ともいえる創業者の姿勢を引き継ぎつつ、2代目社長である秋山大輔氏は、小規模作業場や研究開発部署でも扱いやすい小型研磨機械や少量パックの研磨材料を自社ブランド「AS(エース)」として展開し、同時にBtoB(企業向け)通販業者経由での販売を強化、さらにAmazonなどを通じてBtoC(個人向け)市場にも本格的に参入し販売を強化している。
創業時は卸売を主体としていた同社の売上は、現在約6割が自社製品で構成されており、商品点数も年々増加傾向にある。今後も売上構成比をさらに高めていく意向で、商品開発のさらなる展開にも注目だ。
また、秋山産業ではWeb上での情報発信にも力を入れている。自社ホームページに加え、YouTube、noteやSNSでの情報発信を通じて、研磨に不慣れなユーザーにも正しい知識や使い方を伝えている。

「真面目」で「オモロイ」ものづくり
秋山産業の経営理念は、「人」と「モノ」に“真面目”な商い、「社会」と「社員」に“オモロイ”商い。この一文は、同社のものづくりと組織文化の両方を端的に表している。
“真面目”さは、製品に対する誠実な姿勢に表れる。例えば、製造業務や出荷業務ではダブルチェックを社内ルールとしており、場合によってはトリプルチェックを行うほどの徹底ぶりだ。
全社員が自社製品の構造や特性を理解することを大切にしており、「知らないモノは売らない」という精神で日々の仕事に取り組みますという方針が社内には根付いている。去年入社した社員の佐藤さんも、「説明できない製品は売らないという方針がプレッシャーにもなるが、一年経って製品への理解が深まり、責任感を持って顧客対応ができるようになった」と振り返る。
一方で、“オモロイ”は、仕事の中にある工夫や遊び心を大切にする姿勢を指す。
社内の棚にはテーマに沿って社員が考えたユニークな名前が付けられており、日々の整理整頓が自然と楽しいものになるよう工夫されている。また、パート社員の特技を活かした習字教室や、サンドブラストワークショップなどを社内イベントとして定期的に開催している。そうした場をきっかけに、社員同士のコミュニケーションを活性化させ、互いの得意分野を尊重し合う風土が育まれている。

秋山社長は「社員自身が楽しんで働いていないと、お客様に喜ばれる製品・サービスは提供できない。」と語る。取材中も社員同士が冗談を交えながら意見を出し合う様子が見られ、風通しの良い職場環境がうかがえた。こうした日常的なやり取りから、社員が安心して働ける職場づくりに取り組んできた様子が伝わってきた。
上下関係にとらわれず誰もが意見を出し合える風土は、実際の製品開発や改善提案にもつながっている。“真面目”と、“オモロイ”。一見すると相反するように思えるこの2つの価値観を、日常業務の中で自然に両立させている。誠実であることと、楽しむこと。それを両立させる空気感が、製品の品質やブランドへの信頼感にもつながっているのだろう。

当たり前を支える技術を身近に
製品づくり、企業文化、そのいずれにも小規模作業場や研究開発部署のニーズに合わせたものづくりの姿勢が現れているが、その視線はさらに外の社会にも向けられている。同社は2025年、初めてFactorISMに参加する。体験型の「サンドブラストワークショップ」を実施する予定だ。
経営理念に掲げる「社会」と「社員」に“オモロイ”商いを実践すべく、このイベントを“社会とのつながりを深める場”として活用したいと考えている。開催まで2ヶ月を切った現在、積極的に準備を進めている段階だ。
今回のFactorISMのテーマは「五感」。秋山産業はその中でも「触れる」にフォーカスしたサンドブラスト体験を提供する。
実際に機械を使い、ガラスを削り模様を施す工程を来場者自身が手を動かして体験できる。単に「削ってみよう」というアクティビティではなく、研磨の楽しさ、そして表面の変わりざまを触れることで感じてもらうことをめざしている。
「たとえば、身の回りにあるものでも、ザラザラとした表面がなめらかな手触りへと変化したり、なめらかな表面がザラザラした手触りへ変化するのは、研磨という工程を経て初めて成立する“当たり前”です。それを、自分の手で感じてほしい。」と秋山社長は語る。
このイベントに向けて、事前にプレイベントなども開催し、実際の作業工程にかかる時間や、どこに一番“面白さ”を感じてもらえるかなど、来場者の体験設計を徹底してシミュレーションをしているという。今回の体験から、参加者に何を“持ち帰って”もらうのかを真剣に考える姿は、まさに秋山産業らしい誠実さの現れだ。
「FactorISMを通じて、秋山産業ってこんな会社だよと、家庭の食卓でふと話題にのぼるような存在になること。それが今回のイベントを通じて目指すひとつの成果だ。」と、イベント担当の佐藤さんは語る。
製品・サービスを売るだけではなく、“会社そのもの”が記憶に残る存在になりたい。そんな願いが、このイベントに込められている。