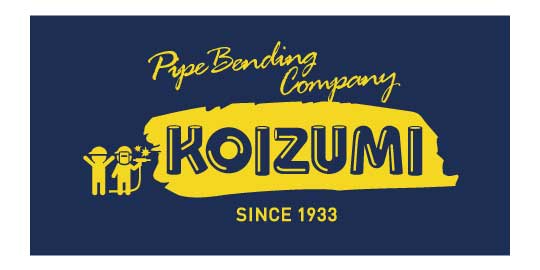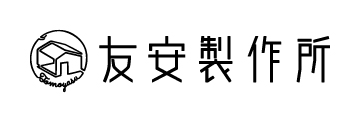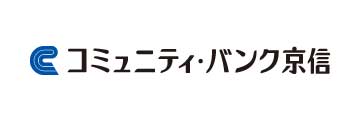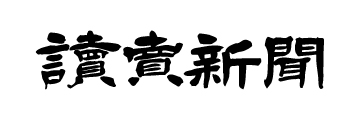“非合理”を大切に、ものづくりの先頭に立ち続ける
Episode
♯語り手
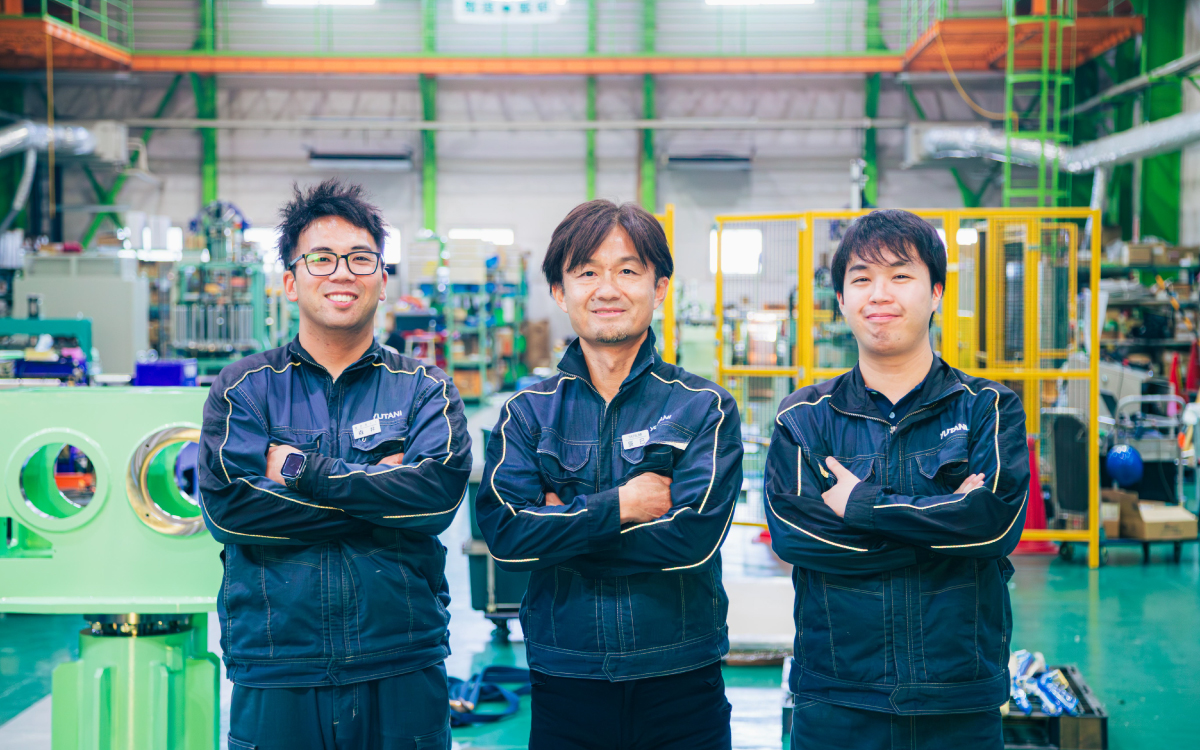
代表取締役社長 辰巳 芳丈
資材グループ 主任 森井 啓太
営業技術部 岡 翼
一気通貫の体制で、未来を見据えた製造現場へ
自動車や冷蔵庫、洗濯機といった工業製品の多くは、薄い金属板を加工するところから始まる。鉄やアルミなどを帯状に巻いた「コイル」と呼ばれる素材を切断し、平らに伸ばし、必要なサイズや形状へと加工していく。その“はじまりの工程”を支えるのが、ユタニのつくる「コイルライン」だ。
創業は1937年。今年で88年目を迎えるユタニは、コイルラインシステムに特化した産業機械メーカーとして、業界内でも高い技術力と対応力で知られ、国内はもちろんのこと、世界の製造現場に導入されてきた。
特に、金属の特性を深く理解し、加工時に生じる歪みや反りをミクロン単位で整える「レベラー」と呼ばれる装置の設計・製造に長けており、自動車や家電メーカーを中心に、国内外の製造現場を支えている。

これまでも、顧客のニーズに応じてオーダーメイドで製品を開発してきたユタニ。しかし昨今、製造現場のニーズ、課題は一段と複雑化している。
「お客様の現場もかつては3人で担当していた作業を、今では1人でこなさなければならないケースも珍しくない」と語るのは、4代目の辰巳社長。
そうした製造現場の課題に応えるべく、ユタニが力を入れているのが、設備の上流から後工程までをワンストップで提供していくことである。これにより、顧客側は複数メーカーに見積もりを依頼し、仕様をすり合わせる手間や時間を負担することなく、一社完結で相談から導入・運用までを任すことができる。
そのため、近年は、人の腕のように自在に動く「多関節ロボット」や、製品の自動搬送の導入も進めている。こうした自動化への対応も含めて、「ワンストップ」で提案できる体制は、時間短縮・品質の一貫性・柔軟なカスタマイズ対応という面で顧客にとって大きな利点となるだろう。
さらに、日本国内や台湾のメーカーとの協業も開始。自社製品との組み合わせによって、より多様な要望に応えられる体制が整いつつある。敷地内には現在新工場も建設中で、今後の発展がますます期待されている。
設計、製造からメンテナンスまで一気通貫の体制によって、納品後もお客様に寄り添ったサポートを実現しており、「納品して終わりじゃない。現場で納品した機械がしっかりと稼働して、お客様の役に立ち、20-30年生産設備として活躍し続けることが私たちの仕事」と辰巳社長は語る。ユタニのものづくりへの想いがこの一言に凝縮されている。さらに2025年6月には、新入社員が手掛けたマスコットキャラクター「ゆたどん」と「レベラーくん」が誕生。工場の仕事や機械の魅力を、より親しみやすい形で伝える役割を担っている。社内でも社員がアイデアを出し合いながら作り上げたキャラクターで、社外向けのイベントやパンフレット、SNSなどでも活躍が期待されている。製品そのものが堅く見えがちなので、より多くの人に“楽しさ”や“面白さ”とともにユタニの魅力を届けたいという思いが込められている。

“非合理”にこそ、応える価値がある
ユタニの理念は、「笑顔から笑顔を生むモノづくり」。自動化・省力化・独創化によって世界のモノづくりに貢献し、安全で便利な製品を提供することで、社会全体の暮らしを豊かにすることをめざしている。その根底には、「お客様のために、できる限り応える」という精神がある。
この理念は単なるスローガンにとどまらず、日々の業務の中で社員一人ひとりに浸透している。例えばユタニでは、効率や生産性だけを追求するのではなく、一見“非合理”に思えるような業務にも価値を見出しているのだ。
「効率は確かに大切ですが、非合理なこと、例えば部署間での密なやり取りや、図面や部品寸法の細部まで詰める確認作業ひとつにも価値があります。それをやらなければ、お客様が求めるものには応えられない」と辰巳社長は語る。
こうした考え方に至った背景には、二流、三流メーカーと位置付けられていた時代の苦い経験がある。とにかく受注を優先する風潮の中で、設計や品質への配慮が後回しになり、社員の負担も大きかった。「言われたことを文句言わずにやる。」「長い時間働いた者が偉い」とされるような空気が社内に漂っていた時期もあったという。
「このままでは三流メーカーで終わってしまう」。そうした危機感から、ユタニは“真に選ばれるメーカーになるため”に本気で取り組んだ。その中で培われたのが、細部まで妥協しない、 非合理にも思える確認作業や部署間の丁寧な連携を大切にする姿勢である。
効率だけを追うのではなく、あえて“手間をかける”ことで製品の完成度と信頼を高めていく。その積み重ねがいまのユタニのものづくりの土台となっている。
たとえば、部品製作のスピードや柔軟性において、他社で2週間かかる工程をユタニでは2日で仕上げることもある。これは単に加工技術が優れているからではない。
設計・加工・組立・電気工事までをすべて自社内で一気通貫で担っているからこそ、各工程間の調整や手戻りが最小限で済む。さらに、部品一つひとつが顧客の生産設備全体にどのような影響を及ぼすかを現場レベルで理解しているため、判断や対応も早い。そうした社内連携と顧客理解の深さが、スピードと柔軟性を支えている。
さらに、ユタニでは現場の声や使い手の状況を深く理解したうえで、製品一つひとつが顧客の設備全体にどのように影響を与えるかまでを踏まえて判断・対応を行う。その結果、スピードだけでなく柔軟性や的確さでも他社との差別化を図っている。
こうした体制や姿勢の根底にあるのが、「非合理なことを面倒だと思わず、そこにこそ応える価値があると信じて行動する」という信念だ。確認作業や社内のすり合わせ、部署間の細やかな連携といった“手間”を惜しまないからこそ、完成度と信頼を確かなものにしている。
そのうえで、標準仕様をベースにしながらも、顧客ごとの課題や使い方に合わせて仕様を柔軟に調整していく“セミオーダー”のものづくりこそが、ユタニの最大の強みであり、顧客から選ばれ続ける理由となっている。

触れる体験から広がる、ものづくりの面白さ——FactorISM 2025
今年のFactorISMのテーマは「五感」。その中でユタニが選んだ感性は「触れる」だ。
鉄の重みや、ひんやりとした質感、図面に描かれた部品が少しずつ形になっていく工程...ひとつの製品が完成していく全ての過程を、来場者がその手で触れて体感することができる。
「鉄を削るとどんな形になるのか」「重たい部品はどのように扱うのか」さらには、「組み上がった部品たちをどのように使うのか、動かしていくのか」といった問いに、触れる感覚を通じて自ずと答えが浮かび上がってくるのではないだろうか。
特に“一枚の金属板が、加工と組み立てを経て精密な機械へと変わっていく”という製造のプロセス全体を見渡せる体験は、普段にはない。だからこそ、子どもから大人まで誰もがものづくりの裏側に触れる貴重な機会となるはずだ。
昨年度は、新入社員のアイデアで、工場の部品を活用したオリジナルゲームも登場。輪投げの輪を実際の金属部品に替えたり、配管で風船を膨らませたりと、“機械仕立て”の遊びに、来場者の目も輝いた。今年も同様に、若手社員を中心に、楽しさと学びのある企画が準備されている。
「うちに来てもらえれば、ものづくりを最初から最後まで体験できる。それが、ユタニの一番の魅力だと思う」と担当者の森井さんは語る。”触れる”体験の先に、ものづくりの面白さを感じてもらいたい—そんな思いを込めて、ユタニは今年もFactorISMに参加する。